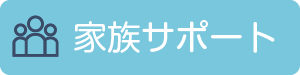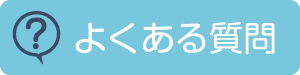研修情報
第九回薬物乱用対策研修会 > 研修会プログラム > 第13講義
薬物乱用者に対する更生保護のかかわり
宇都宮保護観察所
所長 生駒 貴弘
1.更生保護の制度
1)目的
更生保護制度の目的は、基本法である更生保護法に端的に示されている。
第一条 この法律は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるとともに、恩赦の適正な運用を図るほか、犯罪予防の活動の促進等を行い、もって、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを目的とする。
2)かかわる職員の専門性と特性
更生保護制度にかかわる職員は「保護観察官」である。保護観察官は、医学、心理学、教育学、社会学等の専門的知識に基づき、更生保護の事務に従事する(更生保護法第31条)。
また、保護観察官を質量ともに補うのが「保護司」である。保護司は、地域ごとに定められた定数の範囲内で、社会的信望がある民間人に対し法務大臣が委嘱する非常勤の国家公務員である。通常、保護観察対象者の近隣に居住する保護司を担当者として指名しており、対象者との定期的な面接と情緒的交流を基盤として指導監督と補導援護を行い、保護観察所との連絡調整を行っている。
また、刑事上の身柄拘束を解かれた後に帰住する住居がない者等に対し、衣食住の提供や生活指導などを行うのが更生保護施設であり、現在、全国で103施設がある。
3)通常期待されている役割
保護観察の職務の中核は、犯罪をした者や非行のある少年に対し、社会内で「指導監督」と「補導援護」を行い、その再犯防止と改善更生を図ることである。指導監督は、保護観察中に遵守すべき事項(遵守事項)を遵守するよう指導・監督を行ない、遵守事項への違反に対しては、身柄拘束を伴う措置(仮釈放取消し、執行猶予取消し等)をとることもある。指導監督面では、保護観察官が果たすべき役割は組織として統制されている。これに対し、援助的側面である補導援護の内容はケースバイケースで多岐にわたり、特に薬物事犯者の場合に重要なのが関係機関との連携による支援であり、保護観察官にはコーディネーターとしての役割が期待される。
2.薬物乱用者に対する更生保護の役割
薬物乱用者に対する更生保護の役割の中核は、「①薬物再使用の防止」と、「②援助へのかかわりの促進」である。
保護観察所は、保護観察対象者の新たな薬物使用(犯罪)に対しては自ら捜査権は持たず、警察等の捜査機関に委ねる。犯罪として立件されれば遵守事項違反に対する保護観察の取消処分を執行するが、これは事後的な処理であり、あくまで薬物再使用の未然防止を図ることが保護観察の主眼である。「①薬物再使用の防止」の中核となる手段は、簡易薬物検出検査と教育課程を一体のものとして運用する「薬物再乱用防止プログラム」である。また、プログラム受講者以外には、簡易薬物検査を単独で活用している。
「②援助へのかかわりの促進」については、刑の一部執行猶予制度の施行に伴い、更生保護法に、規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対する指導監督の特則が設けられ、薬物依存の改善に資する医療又は専門的援助にかかわるよう指導することなどの新たな規定により、保護観察所の果たすべき役割が明確となった(第65条の3)。
3.薬物乱用者に対する更生保護の課題
第1に、上記(更生保護法第63条の3)の規定は、「本人の意思に反しない」限りにおいて実施できるものであり、また、保護観察所には精神科医療及び薬学の知見を有する職員が配置されておらず、医療の必要性等に関するアセスメントが実施できないため、精神科医療へのかかわりを指導する体制が不十分である。この結果、少なくない対象者が、不眠等を理由に、薬物乱用歴を申告せずに受診し、依存性の高い処方薬を入手して(しばしばアルコールと併用して)使用することがあるなど、精神科医療との連携に課題を抱えている。
第2に、物質使用障害からの回復のための地域支援(医療機関やリハビリ施設等)の絶対数の不足と地域偏在の問題がある。現状では、多くの対象者が、保護観察所が行う処遇プログラムに参加するだけで完結している状況がある。
第3に、薬物使用障害の改善に資する最新の学問的知見や実践を、いかに政策に反映させるかの問題がある。保護観察実施上の義務として専門的処遇を位置付ける場合、保護観察対象者に対して、全国統一的な基準に基づく専門的処遇を受けるよう求めることとなるが、地域の関係機関が実践する専門的処遇が日々進化する中で、各種技法等の効果(エビデンス)をどのように評価し、政策に取り入れていくかということも、今後の課題と考えられる。
4.条件反射制御法の効果に関する統計的検証
上記3の第3の課題に関連し、医療法人社団ほっとステーションにおける物質使用障害がある外来患者に対するCRCTの効果について、統計的な検証研究を行った結果、物質使用障害者の通院治療を継続させる効果、及びその再犯を防止する効果があることを示唆する結果が得られた。その研究結果を紹介する。