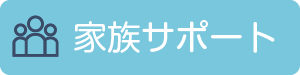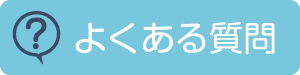研修情報
第九回薬物乱用対策研修会 > 研修会プログラム > 第14講義
矯正施設から社会内施設への情報の提供
一般財団法人成研会結のぞみ病院
診療部副部長 中元 総一郎
薬物乱用者に関する事例においては、それによって生じた害に対する治療やリハビリが、出所(院)後も円滑に開始されることが必要である。だが、ただ単なる啓発や表層的な接触だけでは薬物乱用者が援助機関に足を向けることはない。薬物を止めること、およびそのための治療やリハビリを受けることは、薬物乱用者にとっては多大な労力を要するように感じられるからである。
そのため各関係機関においては、治療の開始や継続に向けた密な働きかけやそのために必要な情報提供が求められる。近年は、一部執行猶予制度や後述する地域生活定着支援事業の創設もあり、矯正施設側や受け入れる地域精神保健行政および民間支援団体の意識も高まっているが、やはり矯正施設内で対応がなされず社会内に放り出された形になっている対象者も、未だに散見される。
最近において経験した事例としては、矯正施設内で覚せい剤による重度の精神病が遷延化し、施設内での投薬により何とか落ち着いたものの、出所時の精神保健福祉法第26条通報に対して自治体精神保健福祉行政が対応せず、また出所時の投薬も行われず、出所数日後当院受診に向かう途中で幻覚妄想に基づいた再犯を犯し逮捕され、勾留中に精神病が悪化したケースがあった。治療が切れ目なく継続されていれば、このケースの精神病再燃悪化はなかったと思われる。
精神病に限らず、薬物反復使用の問題に関しても、矯正施設を出る者に対してもれなく援助に関わるよう働きかけを行えば、薬物乱用を社会から格段に減らすことが可能になる。しかし現状ではまだまだ改善の余地があるようにも感じられる。
過去の調査で明らかになったことを述べる。(今年も同様の調査を行ったが、残念ながら円滑に進行していない現状がある。)矯正施設内で精神病性障害に対する薬剤を規則的に服用していた者が出所あるいは出院する際に、矯正施設が出所後当面の処方を提供しない、対象者に治療の継続を働きかけず診療情報提供も発行しない問題がある。また帰住地の保健所への通報(精神保健福祉法第26条)をしている場合でも情報提供の内容が不十分であることが過去の調査などで明らかになった。
特に、平成18年11月に都道府県と政令指定都市を対象とした調査では上記が明確となった。47自治体(78%)から回答を得たが、その47自治体に対して平成17年度中に行われた第26条通報で薬物が関連していると思われるケースは643件であった。
それらの通報書類の字数について、「500字以上」「250字以上500字未満」「250字未満」に分類して回答してもらったところ、それぞれ130件、196件、315件であった。
入院が必要と記載され、おそらく矯正施設内でも病状が活発であっただろう32件に関しては、「500字以上」が25件と豊富な情報を提供する傾向だが、矯正施設内で目立たなかった事例に関しては、ほとんど内容のない通報を行っていることが一目瞭然であった。
平成28年にも、近畿地方の府県政令都市(10自治体中、6自治体回答)に同様の調査を行ったところ、平成27年における第26条通報145件中500字以上が5件、250字以上500字未満が105件と、平成18年調査に比べれば改善の傾向がみられる。
しかしながら、薬物事犯で服役をしながら出所後治療が必要ない事例が、上記調査が示すほど多いのか疑問である。もれなく対象者の病状や行動特性を評価し、出所後の治療継続やリハビリの開始に向け、対象者や社会内機関に対して働きかけるべきではないのだろうかと考える。
第26条通報を受けた都道府県の対応も問題のあることが明らかになった。特に、措置が不要な者に関しての治療継続に向けた働きかけや通院が見込まれる医療機関への情報提供を積極的に行わない態勢がみられた。
上記のように情報提供や対象者への働きかけを積極的に行う根拠については、もちろん矯正の三大目的の一つである、「更生・社会復帰」という明確なものがある。これらは昨今の刑事政策の方向性でも明らかだが、他の二つの目的である「危険人物の排除」や「応報感情を満たす」ことよりも優先されるべきである。
それでも情報提供が円滑に行われない理由として、対象者における自己決定権や自己情報コントロール権など、対象者のプライバシーに属する部分に敏感になっている関係者が多いことがある。
特に自己情報コントロール権説に関する誤った解釈が我が国に流布されている。この説は米国のウエスティン教授が英米法系国家に特有の類型的研究の中でプライバシーの一つの類型として述べたものである。しかし、日本では大陸法系国家に特有の要件的思考の中で定義として受け取られてしまった。類型的思考の中では、コントロール権が失われても必ずしもプライバシー侵害にはならないが、それが定義として考えると、もしコントロール権が失われると即プライバシー侵害になってしまう。これはウエスティン教授の意図とは異なる。
プライバシー権は、その発生の経緯から考察しても、一部の人権主義者が主張するような自然権ではなく、また公共の利益に優先するものでもない。従って、薬物乱用者回復支援における個人情報の取り扱いは、自己情報コントロール権説からではなく、情報化時代における「公共性」と「個の尊厳」の調和の観点から考えるべきなのである。
対象者の「自己情報コントロール権」などのプライバシー権と、他の要請との間のバランスが重要であるとの理論を実証するために、財)大川情報通信基金の助成を受け、以下の調査を行った。演者が平成23年3月まで勤務した、独立行政法人国立病院機構 下総精神医療センターの薬物関連精神疾患専門病棟に入院した患者に対して、病院から各機関への情報提供に関するケースを10個挙げ、それぞれが患者の同意が必要か、必ずしも必要でないかを問うた。
その結果、患者の利益や公共の利益を保護する必要性が高い場合には、患者の同意なくとも情報提供はやむを得ないとする傾向となり、逆に患者の利益を阻害するだけで、公共の利益にも繋がらないような情報提供に関しては許さないとする傾向がみられた。要は、必ずしも「自己情報コントロール」が優先されるわけではなく、患者のプライバシーの保護は患者の他の利益、ならびに公共の利益とのバランスで考慮されるべきだという考え方を支持するものである。
さて、従来の精神保健福祉行政や更生保護行政に加えて、平成21年度から各都道府県に整備されてきた「地域生活定着支援事業」が、社会内での治療・リハビリを継続ないし開始する上で重要な役割を担いつつある。
だが現状では、本人の希望を待たねばならないことや、精神作用物質の反復使用の問題だけでは(精神障害を合併しなければ)その対象とならないという問題もある。従って対象となる者には高齢者が多く、精神作用物質の反復使用の治療より、慢性化した精神的・身体的合併症の治療が主になってしまう場合が少なくなく、当然社会復帰も難しくなる。合併症が進行する前に介入を行う制度設計が望ましい。
また、地域生活定着支援センターが、対象者、矯正施設、保護観察所、生活保護行政、病院、社会復帰施設や老人介護施設など、すべての分野の機関などとの折衝を請け負っていることも問題と思われる。