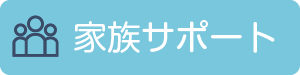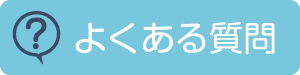研修情報
第九回薬物乱用対策研修会 > 研修会プログラム > 第15講義
薬物事犯の裁判における弁護活動
髙橋洋平法律事務所
弁護士 髙橋 洋平
1.薬物事犯の裁判の問題点
日本の薬物事犯の裁判は、厳罰主義が基本であり、1回目は、無条件で懲役1年6月・執行猶予3年であっても、2回目以降は、ほぼ実刑判決である。
裁判の専らの関心は、刑事責任の重さであり、それがどの程度の量刑(軽いか重いか)になるかということであり、薬物依存からの「治療」という視点が軽視されている。刑事弁護の方法もパターン化し、被告人の「反省」の上、家族らの「監督」、そして、「就労」を重視しているものが多い。
2.問題点に対する改善策
(1)薬物依存からの回復には、治療が重要(事案によっては必須)であることを裁判官、検察官、弁護士の共通認識にする必要がある。
(2)被告人を犯罪者として弁護するよりも、根が深い薬物依存者とみて、その回復の手立てを考える弁護が望ましい。
(3)症状が軽度な者から重度の者まで様々であり、精神疾患や障害がある場合、そうでない場合など、事例ごとに薬物依存の原因も様々である。
(4)薬物依存者の症状に応じて各機関と連携し、それぞれの被疑者・被告人に応じたケアを行うことが必要である。
3.刑事弁護の限界
法律上の弁護人の関わりは、裁判が確定するまでであり、判決確定後は、基本的・原則的には薬物依存者(被告人)に弁護人(弁護士)が関わることはない。
また、弁護人が執行猶予で釈放された被告人や、実刑判決を受けた被告人の刑務所収容後の薬物依存からの回復のためのケアを行うことは難しい。
4.刑事弁護の限界に対する打開案
裁判後のことを考え、早期段階から、継続的に被告人の治療に関わっていく機関との連携を大切にし、支援チームの一員になってもらう。
5.被疑者・被告人に治療・回復の機会を提供する方法
(1)被疑者段階(身柄)
援助体系と連携して治療・回復の機会を提供することは、逮捕・勾留が解消されない限り、通常は期待できないが、面会などを通じて関わってもらう。
(2)起訴後未決勾留の段階
ア.保釈制度の活用にあたっては、援助体系との連携が必要である。
(ア)保釈制度
(イ)保釈の事例紹介
(ウ)保釈の限界
執行猶予期間中の再犯については、裁判所は容易に保釈を認めない傾向にある。執行猶予満了後についても、執行猶予満了後間もなくの再犯についても同様の傾向にある。
イ.回復・治療のための措置
(ア)援助体系からの面会、通信教育
(イ)ダルクヘの通所・入寮、下総精神医療センターへの入院
6.裁判における弁護方法・目指すべき判決
(1)初犯の者
保釈申請し、援助体系と連携して治療を行い、その成果を裁判で報告する。
執行猶予付判決を導き、薬物治療・回復を行える環境を整える。
現在の裁判では、初犯の者はほぼ確実に執行猶予が付く。即決裁判制度の場合、治療の措置を取る暇もなく釈放され、連絡が取れなくなる場合も多い。
もっとも、初犯でも重度の依存の場合、弁護人の方から保護観察付の執行猶予を要望することを考えてはどうか。
(2)再犯の者
保釈を取ることができる場合は、援助体系と連携して治療を行う。
① 被告人を民間の薬物依存症回復施設である「ダルク」や「下総精神医療センター」において治療を行い、公判において、その間の治療の成果・効果を裁判官に報告する。
② 執行猶予の要件を満たす者については、再度の執行猶予を目指す。
③ 執行猶予の要件を満たさない者については、懲役刑の減軽を目指す。
④ 刑の一部執行猶予を目指す。
【参考】
・執行猶予期間が経過した後、2年から2年10か月ほどの再犯につき、再び執行猶予判決が得られたケース
・仮釈放後、間もなくの再犯につき、刑の一部執行猶予判決が得られたケース
・執行猶予中(保護観察付)の再犯につき、刑の一部執行猶予判決が得られたケース
・保釈中の再犯につき、制限住居を病院に設定し、再び保釈が許可されたケース
7.第一審判決時までに治療が終了するように工夫する
第一審判決時までに治療が終了するように工夫するのが裁判及び治療の観点からは有効かつ適切である。第一審判決(実刑判決)時において治療が終了していない場合は、個別的な事情によっては、控訴後、再度保釈申請を行うこととし、治療が終わった段階で控訴を取り下げる等の工夫も必要であろう。
8.今後の薬物事犯の裁判への対応
裁判所に対し、薬物事犯者を通常の犯罪者と同視するのではなく、心と体に病を持つ者であり、治療回復措置を必要としている者として捉えてもらうための努力をすべきである。今後とも、刑罰(懲役)より治療を重視し、社会内での更生(立ち直り)を目指していくべきであろう。