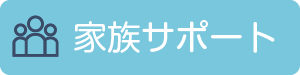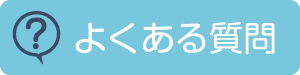研修情報
第九回薬物乱用対策研修会 > 研修会プログラム > 第18講義
薬物事犯者に対する検察の業務
前橋地方検察庁
検事正 森 悦子
検察官は公訴官であり,捜査・公判を通した検察権の行使によってのみ薬物事犯撲滅に寄与することができる。薬物事犯撲滅のためには,需要の根絶と供給源の根絶が必要であり,検察官の役割として特に期待されるのは供給源の根絶ではないかと思われる。すなわち,薬物の密売事犯に対する適正な捜査処理,適正な科刑の実現である。本講義では,刑事司法における検察官の役割について触れた上で,薬物事犯の撲滅に向けて検察官として何が出来るのかを説明させていただく予定である。
1.薬物事犯者が検察庁に送致されてからのかかわり
1)刑事司法手続における検察官の役割(検察庁法4条,6条)
検察官は,公益の代表者として,個々の刑事事件について公訴を提起すべきかどうかを判断し,公訴を提起し又は公訴を提起しない権限,及び公訴を提起した場合にはこれを維持遂行し,裁判所に法の正当な適用を請求する権限を有する。
有罪判決が確定した場合には,その刑の執行を指揮する権限,あらゆる犯罪について捜査をする権限も有する。
我が国は,私人による訴追を認めておらず,公訴を提起する権限は原則として検察官のみに付与されており(起訴独占主義),他方で,検察官には,公訴を提起するか否か(起訴か不起訴か)につき,大幅な裁量権が与えられている(起訴便宜主義)。
2)捜査及び検察官による事件処理のプロセス
薬物事犯の捜査の端緒は,職務質問,家族や事件関係者,病院からの通報,関係か所の捜索・差押え,税関検査など様々である。
検察官は,警察官や麻薬取締官などの司法警察員から事件送致を受け,これらの捜査機関と協力して必要な捜査を遂げ,起訴・不起訴の判断をする。その過程で,被疑者を勾留するか否かも第一義的には検察官の判断にかかっている。薬物事犯については,証拠の隠滅や逃走のおそれが高いと認められることが多いため,特別な事情がない限り裁判所に勾留請求をするのが一般的である。
被疑者の勾留期間は,勾留請求の日から最大で20日間であり,その間,検察官は,警察等に対し,補充捜査を依頼したり自ら被疑者,関係者等を取り調べるなどして事案の真相解明に努める。
3)被疑者の取調べ
我が国の検察官は,自ら被疑者・参考人を取り調べるなど,証拠の収集を直接かつ積極的に行うという特色を有している。取調べの機能・目的としては,①被疑者・関係者から供述を得て,犯罪構成要件要素を含む事案の真相を解明すること,②犯罪の主観的要素(犯罪を犯すことの認識など),情状として酌むべき事情等を解明すること,③犯罪組織の情報を入手すること,④被疑者の改善更生に資することなどが挙げられるが,薬物事犯においては,①及び②もさることながら,③及び④に重きを置いた取調べが必要である。
限られた捜査手法の中で,薬物の密売に関わる者や密売組織を検挙し,処罰するためには,末端使用者から薬物入手先の情報を得て密売人を検挙し,さらにその密売人から上位の密売人ないし密売組織の情報を得て順次検挙していくという,いわゆる「突き上げ捜査」を行う必要があり,取調べで被疑者に真相を語らせることが極めて重要な捜査手法となっている。
また,検察官は,再犯防止の観点から,取調べの中で被疑者に真の反省を促し,適切な訓戒をするよう努めており,再犯率の高さに照らすとその効果は微々たるものに過ぎないと思われるものの,初犯の薬物使用者に対してはこのような取調べが功を奏する場合もあると思われる。少なくとも検察官は,取調べが被疑者の改善更生に資する場合があることを信じて,日々,取調べにあたっているところである。
4)新たな捜査手法について
昨年5月24日に成立し,6月3日に公布された刑事訴訟法等の一部を改正する法律により,薬物事犯等の捜査に「司法取引」と言われる新たな捜査手法が導入されることになった。
そのひとつが「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度」である。これは,検察官が弁護人の同意を条件に,被疑者・被告人との間で,他人の犯罪事実を明らかにするための供述等をすることと引き換えに,不起訴や特定の求刑をする旨の合意をすることができる制度であり,薬物事犯も対象犯罪のひとつとされている。さらに,通信傍受についても,通信事業者の立会いなく傍受を実施できるようになるなど合意化,効率化が図られた。
将来的にはこれらの制度を活用し,密売組織を検挙することが可能になると思われる。
2.裁判における検察官の役割
検察官は,裁判において,起訴した事実を立証する証拠及び刑を決めるに当たり必要と思われる証拠(被告人に有利な証拠を含む)を提出し,裁判所に対し,適正な科刑を求める役割を担っている。
なお,法定刑に無期懲役がある事件(業としての覚せい剤や麻薬等の輸入,営利目的による覚せい剤の輸入,製造,同目的によるヘロインの輸入,製造など)は裁判員裁判で審理される。
前述の法改正により,薬物事犯の裁判で活用できる制度として,刑事免責制度が導入された。これは,裁判所の決定により,免責を与える条件の下で,証人にとって不利益な事項についても証言を義務付けることができるようにする制度であり,上部被疑者・被告人の犯罪の立証が容易になることが期待できる。
また,昨年6月施行の刑の一部執行猶予制度は,刑事施設内での専門的処遇に引き続き,社会内でも専門的処遇を行い,薬物依存の改善を図るものであり,再犯防止の一方策として期待されている。検察官としては,同制度が適切に運用されるよう,裁判所に対し,必要な証拠を提出して的確な意見を述べることが必要である。