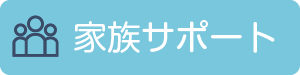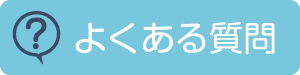研修情報
第九回薬物乱用対策研修会 > 研修会プログラム > 第8講義
薬物乱用対策における回復支援施設の役割
一般社団法人 千葉ダルク
代表理事 白川 雄一郎
DARC(ダルク)は1985年6月に東京都の荒川区で産声をあげた日本ではじめての民間の薬物依存症の回復支援施設である。Drug Addiction Rehabilitation Center
の頭文字をとってDARC-ダルクとよんでいる。
ダルクも今年2017年で創設32周年を迎え、今日現在、全国約70か所以上で活動をしている。約30年前の設立当初から米国のアルコール使用障害からの回復のための当事者による自助グループAAを基とする12ステップ・プログラムとグループ・セラピー(ミーティング)をほぼ唯一のプログラムとしてきた。その位置づけも医療・矯正施設と社会との中間施設であり、その運営もほとんどが当事者の常勤職員によっておこなわれている。
その活動で医療機関との連携はダルク利用者の精神障害治療のための通院診療とその増悪期や薬物、アルコールなどの再使用時のデトックスや離脱のための入院治療でのかかわりと精神科医療機関に入院中のクライアントの退院後の行き場としてのかかわりがある。
千葉ダルクも今年4月で開設14年となり、昨年7月には一般社団法人化、そして10月より生活訓練の障害福祉サービスの事業所としての活動を始めた。そうした中で、これまでの下総精神医療センターとの連携の中で互いの役割が大分整理されてきた。
ダルクの役割は社会復帰のための生活訓練、段階をふんでの就労・自立、そして社会復帰後も薬物を使わない生活を維持するための自助グループへの橋渡しやダルク退寮後も施設への立ち寄りや渇望の増大時の避難所として、またそこへの所属感を維持してもらうことである。
医療機関の役割は薬物のデトックスや離脱、薬物起因の精神障害の軽減であろう。
そして下総精神医療センターでの条件反射制御法実施によりクライアントの薬物に対する渇望を最小限にすることにより、ダルクでは社会復帰のための生活訓練や人間関係の形成のトレーニングをして自立していくという過程がスムースに行うことができうる。
また、無限大連携のなかのダルクのような回復支援施設での尿検査の実施は、施設の雰囲気づくり、対外的なアピール、それと入寮期間中の規制薬物の使用者の処遇に選択の幅をもたせられる等の理由で有用であると考えている。昨年の一般社団法人化と同時にアイスクリーンという唾液による薬物検査キットを定期購入し、基本的に千葉ダルク内の全クライアント(スタッフも含む)を対象に薬物検査を行っている。
当初、下総精神医療センターの十病棟内で行われている条件反射制御法については 2010年4月より千葉ダルクの責任者が毎週月曜日その作業に研究補助員として立ち会い、その効果と作業手順を十分に理解した後、同センターでこの治療を維持ステージまで終えたクライアントについてはダルク内で負の刺激と想像摂取のみを実施していた。
当初、疑似摂取を行わなかった理由は疑似キット―特に注射器と二プロキット、疑似覚せい剤をセンターの病棟内のように個人に所持させることは本人や周りのメンバーの「寝た子を起こす」ことになると危惧したからである。
その後、千葉ダルクも職員体制が充実してきたためデイケアセンターと九十九里ハウスの二か所で希望者の想像ステージを個別に実施することを開始した。
そして、2012年12月からは千葉ダルクの正式のプログラムとして、条件反射制御法の維持ステージを行うこととし、それまですでに行っていた負の刺激、想像に加えて、注射器と二プロキット、疑似覚せい剤等を用いた物質摂取の疑似をも開始した。当初、心配された事故などはなく、安全な回復の場としての雰囲気を作ることの助けになっていると感じている。
また、これらの千葉ダルクでの実績をふまえ、条件反射制御法学会では2014年度、日工組の助成事業として社会復帰施設への条件反射制御法普及のための研修会を四回開催した。
そこには20か所のダルクが参加したが、過去に医療機関で条件反射制御法の第三ステージまで終えたクライアントを受け入れた施設は10か所あるが、そのうちダルクで維持作業を続けたケースは6か所にすぎない。そして昨年来、下総精神医療センターで条件反射制御法を終えたクライアントの受け入れ先となった4か所のダルクには維持作業実施の基本マニュアルを作成してもらい実施している。
しかし、18か所のダルクでスタッフが理論や実施方法に対する理解を深め、人員やスペースを確保できればクライアント本人が希望すれば条件反射制御法の維持作業を実施したいと考えている。